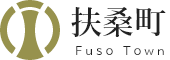70歳から74歳の方の国民健康保険
70歳になると、医療機関での窓口負担割合や高額療養費の限度額などが、それまでと異なってきます。
また、75歳になると、後期高齢者医療に移行します。
資格確認書と高齢受給者証の一体化について
70歳から74歳の方にお送りしていた高齢受給者証(医療費の自己負担割合を示した証)は、令和7年8月1日以降資格確認書に一体化(医療費の自己負担割合を資格確認書に記載)されました。また、マイナ保険証をお持ちの方は、「資格情報のお知らせ」に自己負担割合が記載されています。
新たに70歳となる方へは、70歳を迎える誕生月(1日が誕生日の方は前月)の下旬に、自己負担割合を記載した資格確認書(マイナ保険証をお持ちではない方)または、資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)をお送りします。
医療機関窓口での自己負担割合について
自己負担割合は、誕生日及び所得に応じて2割・3割となっています。
- 国民健康保険に加入されている世帯の中に、町民税課税所得金額(注1)が145万円以上の70歳から74歳の被保険者(加入者)が1人以上いる場合、自己負担割合は3割となります。
- 平成27年1月以降、新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、旧ただし書所得(注2)の合計額が210万円以下の場合は、自己負担割合は2割となります。
- 国民健康保険に加入されている世帯の中に、70歳から74歳の方の被保険者が1人の場合で収入が383万円未満、2人以上の場合で収入合計が520万円未満の方につきましては、申請いただくことで自己負担割合が3割から2割となります。
- このほか、自己負担割合が3割負担となった方で、次の3つすべてに該当する場合は、申請いただくことで自己負担割合が3割から2割となります。
- 当該被保険者の課税所得が145万円以上で収入が383万円以上の場合
- 同一世帯で他に70歳以上75歳未満の被保険者がなく、特定同一世帯所属者(注3)がいる場合
- 当該被保険者と特定同一世帯所属者(注3)の収入の合計額が520万円未満の場合
- 注1:所得の無い19歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯主の方は、年少扶養控除廃止に伴う調整控除があります。
- 注2:旧ただし書所得とは、所得金額から43万円を控除した金額です。
- 注3:特定同一世帯所属者とは「後期高齢者医療制度に該当したことにより国民健康保険の資格を喪失した方で、継続して同一の世帯に属する方」です。
医療機関窓口での1か月(毎月1日から末日まで)の自己負担限度額
自己負担額については、高額療養費をご確認ください。
医療費が高額になる場合は…
現役並み所得者2・1、低所得者2・1に該当する世帯の70歳から74歳の方で、入院や高額な手術・治療・投薬などで医療費が高額になる際に、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口で提示いただくと、自己負担限度額までとなります。詳しくは限度額適用認定証等をご確認ください。
75歳になったら…
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療(扶桑町は「愛知県後期高齢者医療広域連合」)に加入します。
後期高齢者医療の資格確認書は75歳の誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末頃に送付されます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。