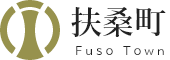特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」
扶桑町ではまだ発見されていませんが、愛知県内でクビアカツヤカミキリが2012年に発見されてから、生息範囲及び被害が拡大しています。
「クビアカツヤカミキリ」とは
クビアカツヤカミキリは、2から4cmの大きさのカミキリムシで、全身が光沢のある黒色、胸の一部が赤いのが特徴です。中国、朝鮮半島、ベトナム北部等が原産地の外来種で、幼虫がサクラ、ウメ、スモモなど主にバラ科の樹木を食害し、場合によっては枯死させます。
2018年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づく特定外来生物に指定され、飼養、保管、運搬、輸入、野外への放出等が原則として禁止されています。
愛知県でも名古屋市、津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、蟹江町、飛島村で、街路樹のサクラを中心に本種により木が枯れる被害が発生しています。
形態
成虫の特徴
体長は約2から4cmで、全体的に光沢のある黒色、前胸背板(首のように見える部分)が赤色で、とげ状の突起があります。
オスの触角は体長の1.7倍ほど、メスの触角は体長より少し長い程度です。
5月末から8月頃に蛹から羽化して成虫になります。越冬は行いません。動きが素早く、驚くと飛ぶこともあります。
羽化してすぐに繁殖行動を行い、メスは木の幹や樹皮の割れ目などに産卵します。
(メスは1匹あたり300~1000個程度産卵すると言われています。)
幼虫の特徴
サクラ、モモ、スモモ、ウメなどのバラ科樹木や、カキ、ポプラなどの樹木に穿孔し、加害します。
樹皮の割れ目などに産卵された卵から孵化し、樹木内部に侵入します。
樹木の生木(形成層付近の辺材)を摂食し、うどん状のフラス(フンと木くずが混ざったもの)を排出しながら樹木内で2~3年かけて成長し、蛹を経て成虫になります。

「クビアカツヤカミキリ」の成虫(写真提供:愛知県)

フラス(フンと木くずが混ざったもの)(写真提供:愛知県)

たくさん排出されたフラス(写真提供:愛知県)
クビアカツヤカミキリを見つけたら
成虫は、見つけ次第、被害拡大防止のため、叩き潰す等して駆除してください。潰すのに抵抗がある方は、市販の殺虫剤をご使用ください。
クビアカツヤカミキリによるものと疑わしい状況を発見した場合は、可能な範囲で写真を撮るなどし、環境課(92-4112)までご連絡をお願いします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全部環境課環境グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4112 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。