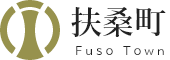特定外来生物「オオバナミズキンバイ」
見た目はきれいでも恐るべき繁殖力を持つオオバナミズキンバイ。鮮やかな黄色い花を咲かせ、湖沼やため池等一面に広がります。現状では、水利施設への被害はほとんど確認されていませんが、琵琶湖で爆発的に増えていることから、水利施設に侵入すれば、通水障害などを起こす恐れがあります。
愛知県内では、令和7年7月に豊田市内の御船川および西中山川で初確認され、駆除活動が進められています。
「オオバナミズキンバイ」とは
オオバナミズキンバイは、南アメリカ及び北アメリカ南部原産の多年生の浮葉~抽水~湿生植物で、日本では、2007年に兵庫県加西市で発見されました。駆除が極めて難しく、2014年に国から特定外来生物に指定され、現在は近畿地方のほか、東北地方、関東地方、九州地方でも定着が報告されています。繁殖生態については、種子繁殖と3月から11月にかけて茎の断片による栄養繁殖をします。冬季は低温で大半が枯死しますが、生き残った茎断片から発根、再生します。種子は越冬可能で、泥中に埋没することで休眠打破すると考えられます。
また、近縁種間に交雑親和性があることから、絶滅危惧種2類のミズキンバイやケミズキンバイとの交雑や遺伝的攪乱を引き起こす可能性があります。近縁種には似た種も多いため、同定の際には注意が必要です。

オオバナミズキンバイ(環境省提供)
見分け方
オオバナミズキンバイの見分け方については「特定外来生物 同定マニュアル」をご参照ください。間違えやすい主な植物はミズキンバイです。
見分け方のポイント
・花弁5枚の黄色い花、径は4~5cm、類似する在来種であるミズキンバイは径2~5cm
・地上茎には粘る毛が密生、在来種のミズキンバイは地上茎・葉ともに無毛
・葉の縁には細毛があり、茎に交互につく

オオバナミズキンバイ(環境省提供)
-
農業水利施設に被害を及ぼす侵略性の高い外来種(オオバナミズキンバイ) (農林水産省) (PDF 1.3MB)

-
特定外来生物の見分け方(同定マニュアル)(81 ページ)(環境省) (PDF 21.3MB)

オオバナミズキンバイを見つけたら
水辺にて、オオバナミズキンバイやナガエツルノゲイトウと疑わしき植物を確認した場合は、扶桑町役場環境課(0587-92-4112)もしくは愛知県自然環境課へご連絡ください。
駆除方法については、拡散防止のための注意事項がありますので、駆除はせずご連絡ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全部環境課環境グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4112 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。