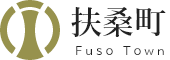特定外来生物「オオキンケイギク」
5~7月ごろに黄色い花が咲いているのを見かけていませんか。それはオオキンケイギクかもしれません。オオキンケイギクは繁殖力が強く強健で、日本に昔からある植物を駆逐してしまうため、特定外来生物に指定されています。

オオキンケイギク(環境省提供)
「オオキンケイギク」とは
オオキンケイギクは、1880年代(明治中期)に観賞用・緑化用として持ち込まれました。育成が容易であり、黄色いきれいな花を咲かせることから、戦後、全国各地で法面緑化等に使用され、その後道路沿いや河川敷、埋立地などに拡散し、その強い繁殖力で在来植物の生育地を奪うようになりました。
日本には自然度の高い河原環境が少なくなっており、そのような環境に生息する希少な在来植物のツツザキヤマジノギク、カワラサイコ、カワラナデシコなどは生育可能な場所が限られているため、オオキンケイギクが河川中流部の河原に侵入すると、そのような在来植物の生育に深刻な悪影響を与える可能性があることから、現在は「特定外来生物」に指定されています。
形態
特徴
5~7月に黄色~オレンジ色の花(舌状花と管状花)を咲かせます。花びらの先端は不規則に4~5つに分かれています。草丈は50~70センチで、葉は細長い楕円形で両面に粗い毛が生えています。
花以外の特徴
・全体的に明るいきみどり色
・茎から生える葉(茎生葉)もあるが、根元からの葉(根生葉)が一斉に生えているものが多い。
・根生葉は全体として細長いへら状で、葉柄の先に細長い楕円形の葉身が続く。葉の先端は尖らない。
・茎生葉も概ね同じ形だが、より葉柄が短く、対生する(左右の葉が互い違いでなく、茎の同じところから生える)ことが多い。
・葉には両面とも粗い毛がある。
・葉脈はあまり目立たない。

オオキンケイギク(環境省提供)
駆除
駆除の方法は、以下の環境省リーフレットをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全部環境課環境グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4112 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。